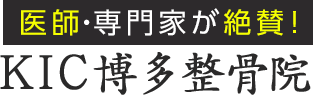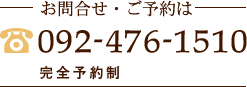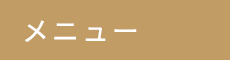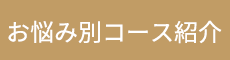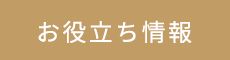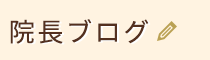目次
- 耳鳴りと血流の関係
- 血流が悪くなる原因
- 血流を促して耳鳴りをやわらげる方法
- 医療機関での血流改善アプローチ
- Q&A:耳鳴りと血流の関係
1.耳鳴りと血流の関係
耳鳴りは、内耳や脳が音を感じる仕組みにトラブルが起きて発生します。
その中でも近年注目されているのが血流不足です。
内耳は非常に細い血管で栄養や酸素を受け取っており、血流が滞ると酸素不足となり、聴覚細胞の働きが鈍くなります。
これが「ジー」「キーン」という耳鳴りを引き起こす要因になると考えられています。
2.血流が悪くなる原因
- 長時間の同じ姿勢(デスクワークやスマホの使用)
- 運動不足による全身循環の低下
- ストレスで自律神経が乱れ、血管が収縮
- 寒冷環境で末梢血管が縮こまる
- 高血圧・動脈硬化など血管の病変
これらが重なると、内耳や脳への血の巡りが悪くなります。
3.血流を促して耳鳴りをやわらげる方法
(1) 軽い有酸素運動
ウォーキングや自転車など、心拍数が軽く上がる程度の運動は全身の血流を促します。
(2) 首・肩・あご周りのストレッチ
耳の周囲の血管は首や肩の筋肉と密接に関係しています。こわばりをほぐすと血流が改善します。
(3) 深呼吸で自律神経を整える
ストレスで交感神経が優位になると血管は収縮します。深く息を吸い、ゆっくり吐くことで副交感神経を働かせ、血管を広げます。
(4) 体を温める習慣
シャワーだけでなく、ぬるめのお湯で15分ほど入浴すると全身が温まり、耳周辺の血流も良くなります。
4.医療機関での血流改善アプローチ
耳鳴りの原因が血流にある場合、耳鼻咽喉科や脳神経外科で血流改善薬(循環改善薬)が処方されることもあります。
また、動脈硬化や頸動脈の狭窄などが関与している場合は、早期の治療が重要です。
5. Q&A:耳鳴りと血流の関係
Q1. 血流が悪くなるとどうして耳鳴りが起きるの?
A. 内耳(耳の奥)は非常に細かい血管で栄養や酸素が供給されています。血流が滞ると、音を感じ取る有毛細胞や神経が十分に働けず、脳が「音が足りない」と錯覚して耳鳴りとして認識することがあります。
Q2. 血流を良くするために、まず何から始めればいい?
A2. 運動や食事改善が効果的です。特に軽いストレッチや有酸素運動(ウォーキングなど)を毎日少しずつ続けることで、全身の血流が改善し、耳の環境も整いやすくなります。
Q3. 耳鳴りがあるときに運動をしても大丈夫?
A3. 基本的には軽い運動は問題ありません。ただし、めまいや強い耳の圧迫感を伴う場合は医療機関での確認が必要です。
Q4. 食べ物で血流を改善できる?
A4. 魚に含まれるEPAやDHA、ナッツ、ビタミンEが豊富な食品は血管の柔軟性を保ちやすくなります。塩分や加工食品の摂りすぎは血流を悪化させるので注意が必要です。
Q5. 血流改善だけで耳鳴りは必ず治るの?
A5. 血流が原因の耳鳴りであれば改善する可能性はありますが、原因が他にある場合は治療方針が変わります。自己判断せず、耳鼻科で原因を特定することが大切です。
まとめ
耳鳴りは単なる耳の不調だけでなく、血の巡りの悪さが関わっているケースがあります。
特に首や肩がこる生活習慣、運動不足、ストレスは血流を低下させやすく、結果として耳鳴りを悪化させる可能性があります。
軽い運動やストレッチ、入浴などで全身の血流を整えることは、耳鳴りの予防・軽減に役立ちます。
耳鳴りが長く続く場合は自己判断せず、専門医で血流の状態も含めて検査を受けることが大切です。